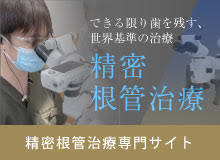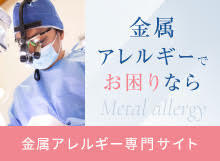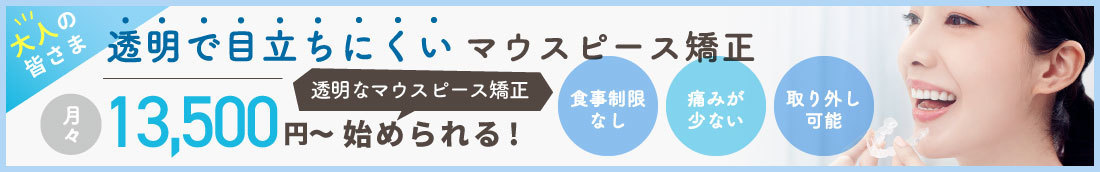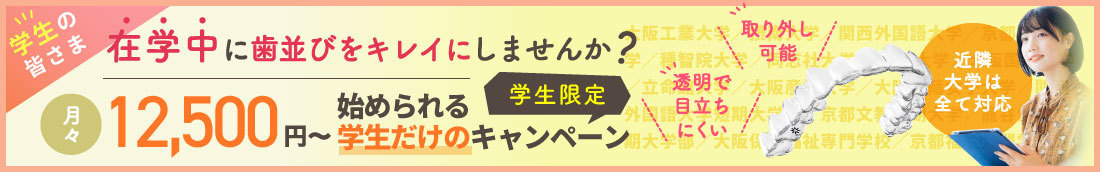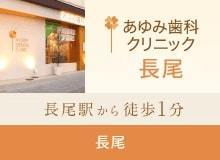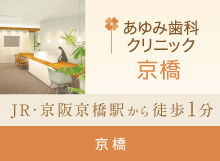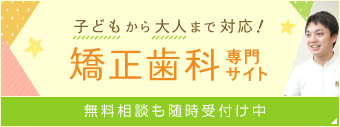歯科豆知識
2025.2.25 現代人は噛む回数が少ない?
昔と今の違い&歯と身体に良い食事を教えます!



こんにちは。枚方市長尾のピノデンタルオフィス枚方長尾の院長、日野です。
はじめに:現代の食生活と「噛む力」の関係
「よく噛んで食べることが大切」と聞いたことがあると思います。しかし、実際に「噛む回数」が健康にどのような影響を与えるのかを意識したことはありますか?
現代の食事は加工食品や柔らかい食品が多く、昔と比べて噛む回数が大幅に減少しています。その結果、口腔内の健康だけでなく、顎の発達や消化機能、さらには脳の働きにも悪影響を及ぼすことが指摘されています。
本記事では、噛むことの重要性や噛む回数を増やすための工夫について詳しく解説し、今日から実践できる方法をご紹介します。
1. 噛むことが健康維持に欠かせない理由
(1) 唾液の働きで口腔内を清潔に保つ
食べ物をしっかり噛むことで唾液の分泌が増え、口内環境が整えられます。唾液は、歯や歯茎を守る重要な役割を果たします。
・ 虫歯を防ぐ … 唾液が酸性に傾いた口内のpHを中和し、エナメル質を保護する
・ 抗菌作用がある … 口内の細菌を抑え、歯周病や口臭のリスクを軽減する
・ 再石灰化を促進する … 初期の虫歯が自然修復されやすくなる
噛む回数が減ると唾液の分泌が少なくなり、細菌が繁殖しやすくなるため、口腔内のトラブルを招く原因となります。
(2) 顎の発達を促進し、歯並びを整える
特に成長期の子どもにとって、噛む習慣は歯並びの形成や顎の発達に大きく影響します。
・ しっかり噛むことで顎の骨が強くなり、歯がきれいに並ぶスペースが確保される
・ 噛み合わせが整い、歯のズレや顎のずれが起こりにくくなる
・ 顎の筋力が鍛えられ、咀嚼能力が向上する
反対に、噛む回数が少ないと顎の成長が不十分になり、歯列不正(歯並びの乱れ)や開咬(上下の歯がかみ合わない状態)を引き起こすリスクが高まります。
(3) 消化を助け、胃腸への負担を軽減する
咀嚼が不十分なまま食べ物を飲み込むと、胃や腸が消化の負担を強く受けることになります。
・ 細かく噛み砕くことで、消化酵素と混ざりやすくなり、胃腸の負担が減る
・ しっかり噛むと満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐ効果がある
・ 消化不良を防ぎ、栄養吸収の効率を高める
早食いの習慣がある人は、胃もたれや肥満のリスクが高くなるため、噛むことを意識するだけで健康維持に大きな違いが生まれます。
2. 噛む回数を増やすための食習慣改善法
(1) 食べ方の見直し
・ 一口あたり30回以上噛むことを目標にする
・ 食事中に箸を置く時間を作り、ゆっくり味わう
・ 食べ物を飲み物で流し込まず、しっかり噛んでから飲み込む
噛む習慣を意識するだけで、咀嚼回数を増やすことができます。
(2) 噛みごたえのある食品を取り入れる
食材選びを工夫することで、無理なく噛む回数を増やせます。
・ 根菜類(にんじん、ごぼう、れんこん など)
・ ナッツ類(アーモンド、くるみ、大豆 など)
・ 弾力のある食品(イカ、タコ、こんにゃく など)
・ 玄米・雑穀米(白米よりも噛みごたえがある)
・ 噛み応えのある果物(りんご、梨 など)
特にナッツ類や根菜類は自然と噛む回数を増やせるため、日々の食事に取り入れるのがおすすめです。
(3) 調理方法を工夫する
食材の調理方法によっても、噛む回数を増やすことができます。
・ 野菜を大きめにカットする(細かく刻みすぎると噛む回数が減る)
・ 硬めに調理する(柔らかくしすぎず、食感を残す)
・ 咀嚼が必要なメニューを選ぶ(例:玄米ご飯+噛みごたえのあるおかず)
3. 昔と今で変化した「噛む回数」
食文化の変化により、現代の人々は昔に比べて噛む回数が激減しています。
【時代ごとの平均咀嚼回数】
・ 縄文時代 … 約4000回
・ 江戸時代 … 約1400回
・ 現代 … 約600回
加工食品やインスタント食品の普及によって、噛まずに食べられる食品が増えたことで、咀嚼回数が減少しています。これが顎の発達不足や消化不良の一因となっているため、意識的に噛む習慣を取り入れることが重要です。
4. まとめ:噛む習慣を身につけて健康な歯と体を守ろう
噛むことを意識するだけで、歯や全身の健康維持に大きな違いが生まれます。
◇ 唾液の分泌が増え、虫歯・歯周病を防ぐ
◇ 顎の発達を促し、歯並びを整えやすくする
◇ 胃腸の負担を軽減し、消化を助ける
◇ 満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐ
◇ 脳の活性化にもつながる
【噛む回数を増やすためのポイント】
★ 1口30回を目安にしっかり噛む
★ 噛みごたえのある食材を取り入れる
★ 調理法を工夫して噛む機会を増やす
毎日の食事で「噛む回数」を増やすことを意識し、健康な歯と体を維持していきましょう!
医療法人隆歩会 ピノデンタルオフィス枚方長尾院長 日野卓哉
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| 午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
※祝日がある週の木曜は診療しております。
休診日:木曜・日曜・祝日