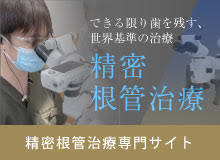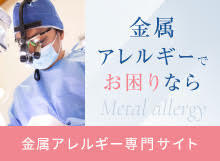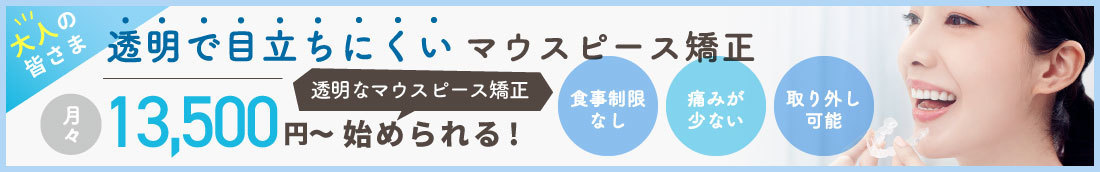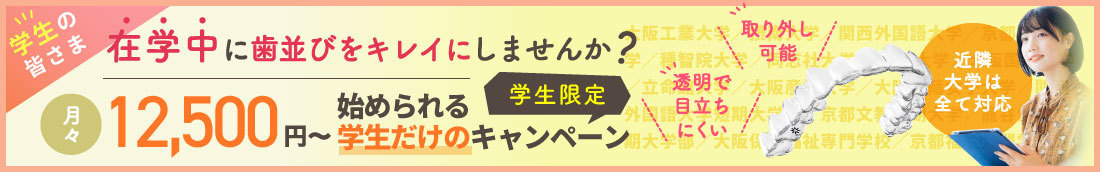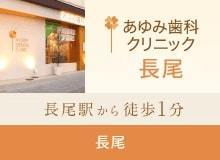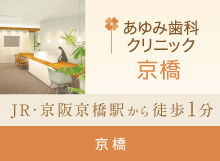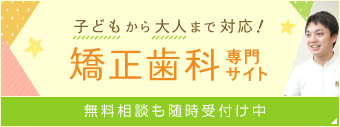歯科豆知識
2025.4.15 よく噛む人ほどボケにくい?
脳を守るために今すぐ見直したい習慣


こんにちは。枚方市長尾のピノデンタルオフィス枚方長尾の院長、日野です。
「最近ちょっと物忘れが増えた気がする」「頭の回転が鈍くなったかも…」
そんな風に感じたことはありませんか?
実は、こうした脳の衰えと密接に関係しているのが、**「噛む力」**です。
よく噛むことは、ただの食習慣ではなく、脳の健康を守るための大切な刺激だということが、近年の研究で明らかになっています。
本記事では、「なぜ噛むことが脳に良いのか?」「噛む力が落ちると何が起こるのか?」といった疑問にお答えしながら、日常生活で取り入れたい“脳を守る噛む習慣”をご紹介します。
噛むことが脳を元気にする理由とは?
食事中の「噛む」という行為は、単に食べ物を小さくするだけの動作ではありません。
噛むことであごが動き、その刺激が脳の特定の領域に直接届くことがわかっています。
特に刺激を受けやすいのが「海馬」と「前頭前野」という部分。海馬は記憶をつかさどり、前頭前野は思考や判断力に関わります。
これらは、認知症の初期にダメージを受けやすい場所でもあります。
よく噛むことで脳の血流が増え、神経細胞の活動が活性化します。つまり、「よく噛む習慣」が、脳の若さを保つ“日常の脳トレ”になっているのです。
「噛まない生活」が脳を老けさせる?
反対に、噛む力が弱くなったり、あまり噛まずに食べる習慣が続いたりすると、脳への刺激が少なくなってしまいます。
その結果、記憶力の低下や判断力の鈍化、注意力の低下といった影響が現れることもあるのです。
実際に、東京医科歯科大学の調査では、奥歯でしっかり噛めない高齢者ほど、脳の一部に萎縮が見られる傾向があると報告されています。
また、日本老年医学会の研究でも、歯が少ない人ほど認知症のリスクが高いことが示されています。
こうした研究結果からも、「噛まない生活」は、知らず知らずのうちに脳の働きを鈍らせている可能性があると考えられています。
噛む力が落ちると起こる、意外な悪循環
噛む力が衰えると、脳への刺激が減るだけでなく、日常生活にもさまざまな支障が出てきます。
-
栄養が偏る:硬いものを避けることで野菜や肉、果物などをあまり食べなくなり、ビタミンやたんぱく質が不足しがちに。
-
食事が楽しくなくなる:噛めないことで食事の満足感が減り、食欲の低下や孤食(ひとりごはん)につながることも。
-
人と話す機会が減る:話すのが億劫になることで外出や会話を避けるようになり、社会的なつながりが薄れてしまう。
このような悪循環は、心の健康や生活の質(QOL)にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
脳を守る「よく噛む習慣」、今すぐできる4つのこと
では、今日からどんなことを意識すればいいのでしょうか?
噛む力と脳の健康を守るためのポイントを4つご紹介します。
1. 歯科検診は定期的に受ける
虫歯や歯周病を放っておくと、噛む力がどんどん低下してしまいます。歯を長く使い続けるために、年に1〜2回のチェックを習慣にしましょう。
2. 噛める状態を取り戻す治療を行う
歯を失ったまま放置せず、入れ歯やインプラントなどでしっかり噛める状態を回復することが大切です。義歯の調整もこまめに行いましょう。
3. 噛みごたえのある食材を食卓に
れんこん、ごぼう、玄米、するめなど、よく噛まないと飲み込めない食材を取り入れることで、自然と噛む回数が増えていきます。
4. 口の筋トレ「パタカラ体操」などを実践
「パ」「タ」「カ」「ラ」と声に出して発音するだけの簡単な体操で、舌や口の周りの筋肉が鍛えられます。毎日の習慣に取り入れるのがおすすめです。
まとめ|噛むことは、最高の“脳のメンテナンス”
「よく噛む人ほどボケにくい」と言われるのは、決して大げさな話ではありません。
噛むというシンプルな行動が、記憶力や集中力を支え、認知症のリスクを減らすカギになるのです。
食事は、毎日必ず行う習慣。その中で「よく噛む」ことを少し意識するだけで、未来の自分の脳を守ることにつながります。
今日から、まずは一口ごとにしっかり噛むところから始めてみませんか?
あなたの脳は、あなたの“噛む力”にかかっているかもしれません。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| 午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
※祝日がある週の木曜は診療しております。
休診日:木曜・日曜・祝日