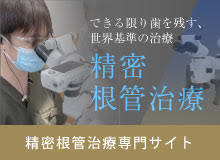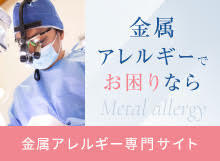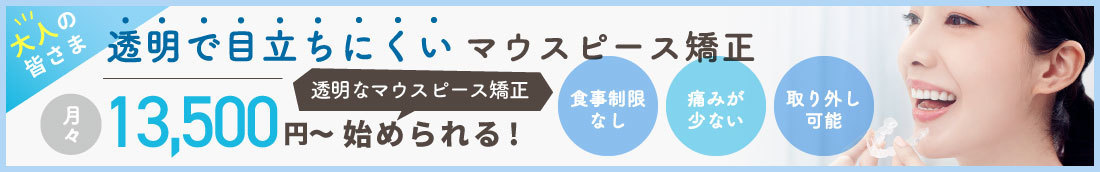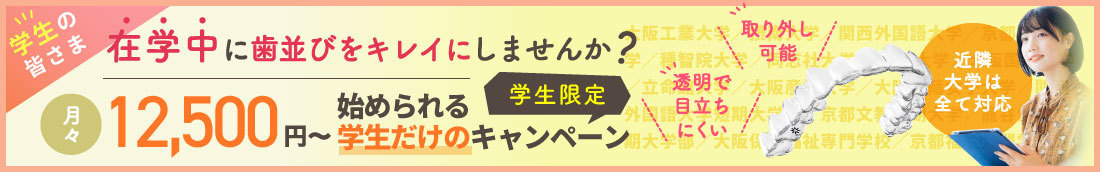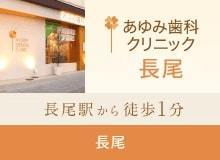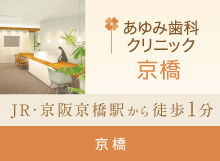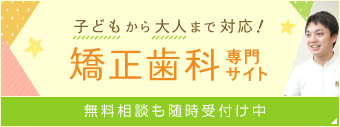歯科豆知識
2025.4.22 歯医者が教える!「口ぽかん」の正体と
子どもの歯並び・健康への影響とは


こんにちは。枚方市長尾のピノデンタルオフィス枚方長尾の院長、日野です。
お子さんの口が無意識のうちにぽかんと開いていることに気づいたことはありませんか?
「ただの癖だからそのうち治るだろう」と見過ごされがちなこの“口ぽかん”状態、実は歯科医の立場から見ると、将来の歯並びや健康に大きな影響を及ぼすサインかもしれません。
この記事では、歯科の視点から「口ぽかん」の原因やその影響、そして保護者ができる対策について詳しく解説します。
「口ぽかん」はなぜ起きる?その正体とは
子どもがぼーっとしているとき、気づけば口が開いている…そんな状態が「口ぽかん」です。
このような状態が慢性的になっている場合、舌の筋力不足や鼻づまり、姿勢の悪さなどが関係している可能性があります。
特に現代の子どもは柔らかい食べ物を好む傾向があり、しっかり噛む機会が少ないため、口まわりの筋肉や舌の機能が十分に育たないまま過ごしていることが少なくありません。
歯並びや顔つきにも影響が?
「口ぽかん」は単なる見た目の問題にとどまりません。
常に口が開いたままでいると、舌が本来の位置(上あご)に収まらず、上あごの発育が阻害されます。これにより、歯が並ぶスペースが狭くなり、出っ歯やすきっ歯、開咬などの不正咬合を引き起こすリスクが高まります。
また、口の周囲の筋肉も使われにくくなるため、顔全体の筋バランスが崩れ、輪郭がぼやけた印象になることも。成長期における「口ぽかん」の習慣は、歯並びだけでなく、見た目や表情にも関係してくるのです。
口での呼吸が癖になっていると…
「口ぽかん」は、多くの場合、口呼吸とセットで起きています。
鼻からではなく、口で呼吸をすることで、さまざまな健康上のデメリットが生じます。
-
喉が乾燥しやすくなり、風邪を引きやすい
-
唾液の分泌が減って虫歯や歯周病のリスクが上がる
-
睡眠中のいびきや眠りの質の低下
-
アレルギーや喘息の悪化にもつながる可能性
口呼吸は、呼吸器の防御機能を回避してしまうため、免疫力の低下にもつながるのです。
鼻呼吸への切り替えがカギ
歯科の現場では、「口ぽかん」の改善には鼻呼吸への切り替えが最も重要とされています。
鼻呼吸を習慣にすることで、空気の加湿・加温、ウイルスのろ過など、呼吸器への負担が減少し、健康面でも多くのメリットがあります。
また、舌の位置が自然と上あごに収まり、上顎の発育が促されることで、歯並びの改善にも良い影響を与えます。
今日からできる対策3選
1. 姿勢を正す
猫背やうつむいた姿勢は、舌が下がりやすくなり、口呼吸を誘発します。正しい姿勢を心がけることが、口を閉じるための第一歩です。
2. あいうべ体操で口まわりの筋肉を強化
「あー」「いー」「うー」「べー」と大きく口を動かす体操は、舌と表情筋のバランスを整える効果があります。毎日数分続けることで、口を自然と閉じる力がつきます。
3. 鼻づまり対策と環境の見直し
アレルギーや風邪による鼻づまりが口呼吸の原因になることもあります。加湿器の使用や寝具の見直し、必要に応じて耳鼻科の受診も検討しましょう。
まとめ|「口ぽかん」は見逃せない成長のサイン
口が開いたままになっている状態を「可愛い仕草」で済ませてしまうのは要注意。
「口ぽかん」は、将来的な歯並びの乱れや健康問題のサインである可能性が高いからです。
大切なのは、早めに気づき、正しい呼吸習慣を身につけられるようサポートすること。
お子さんの成長期における“ほんの小さな違和感”が、大きな変化を防ぐ第一歩となります。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| 午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
※祝日がある週の木曜は診療しております。
休診日:木曜・日曜・祝日