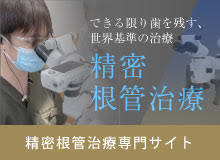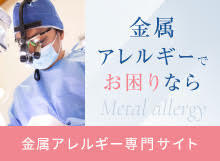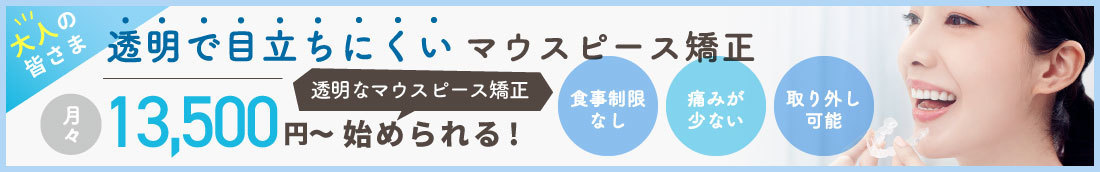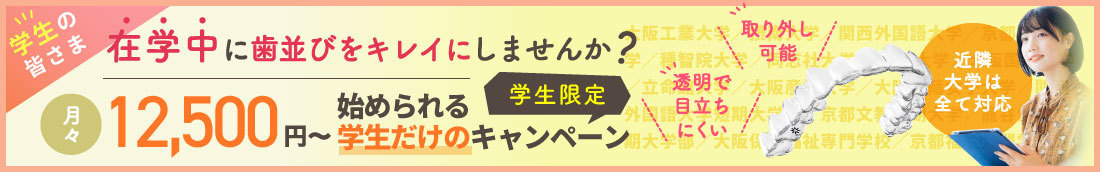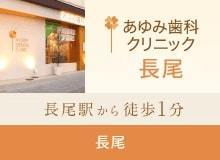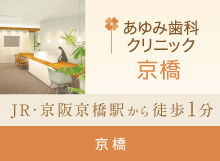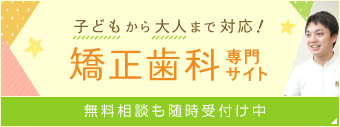歯科豆知識
2025.5.14 こんなにすごい!噛む力を鍛えて一生自分の歯で食べる秘訣


年齢を重ねるにつれて、「できれば最後まで自分の歯で食事を楽しみたい」と考える人は多くなります。
そのためには、歯の本数だけでなく「しっかり噛む力」を保つことが、何より大切です。
噛む力が衰えると、硬いものが食べにくくなるだけでなく、栄養が偏ったり、脳や筋力の働きにも影響を及ぼすことが分かってきています。
この記事では、「噛む力の重要性」と、それを維持するための実践的なコツをお伝えします。
なぜ「噛む力」がそんなに大切なのか?
食事のたびに使っている咀嚼力。実はこれが、全身の健康と深くつながっているのです。
-
食べ物を細かく砕いて消化しやすくする
-
唾液の分泌を促し、口内環境を整える
-
噛む刺激が脳を活性化させ、認知症を予防する
-
顎や顔まわりの筋肉を使い、表情や姿勢を保つ
-
飲み込む力や滑舌、呼吸機能の維持にも関与する
つまり、噛むことは「食べる」だけでなく、「話す」「動く」「考える」ことにもつながる、健康維持の柱なのです。
噛む力が衰えるとどうなる?
噛む力の低下は、次のような変化として現れます。
-
硬いものを避けるようになる
-
食事の時間が短くなり、早食い傾向になる
-
唾液が減って口臭や虫歯が増える
-
食事量が減って栄養バランスが崩れる
-
顎が疲れやすくなり、顔のたるみが目立つ
-
発音が不明瞭になる
また、「噛めないから」とやわらかい食事に偏ることで、咀嚼力がますます落ちていくという悪循環にもつながります。
噛むことで得られる5つの健康メリット
1. 自分の歯を長持ちさせる
しっかり噛むことで、歯ぐきの血流が良くなり、歯の土台が強く保たれます。逆にあまり使われていない歯は、支える骨や歯肉が衰えてしまいます。
噛む力を維持することは、歯を「残す力」でもあるのです。
2. 認知症予防にも効果的
噛むことで脳が刺激され、記憶や判断を司る「海馬」が活性化すると言われています。
実際に、咀嚼回数が多い人ほど認知症の発症リスクが低いという研究報告もあります。
3. 食事の満足度アップ・肥満防止
よく噛んで時間をかけて食べると、満腹中枢が働いて食べすぎを防ぎます。
「ひと口30回」を目標にすると、自然と量が減っても満足感が得られ、ダイエットや血糖値コントロールにも役立ちます。
4. 姿勢やバランスの維持に関係する
噛む筋肉は、首や肩、体幹とも密接に関係しています。噛む力が弱くなると、姿勢が崩れたり転倒しやすくなったりするリスクも。
「よく噛む人は転びにくい」といわれるのは、こうした背景からです。
5. 唾液が増えて口内のトラブルを防ぐ
咀嚼によって唾液腺が刺激され、唾液の分泌が促されます。唾液には殺菌作用・消化促進・粘膜保護などの働きがあり、口腔内を清潔に保つうえで欠かせません。
噛む力を鍛える習慣とは?
● 硬めの食材を意識して選ぶ
れんこん、玄米、こんにゃく、ごぼうなど、自然と噛む回数が増える食材を食事に取り入れてみましょう。
調理のときに少し歯ごたえを残す工夫をするのも効果的です。
● ひと口ごとにしっかり噛む癖をつける
「とりあえず噛む」のではなく、「意識して噛む」ことが重要です。
テレビやスマホを見ながらではなく、食事に集中し、1口30回を目安に丁寧に咀嚼しましょう。
● 歯科での定期ケアを欠かさない
虫歯や歯周病が進行すると、噛むこと自体が苦痛になります。
定期的な歯科検診とメンテナンスを受け、自分の歯で快適に噛める状態を維持しましょう。
まとめ:噛む力を保つことは「生きる力」を守ること
噛む力は、年齢とともに自然と落ちていきます。
しかし、意識と習慣次第でその低下を防ぐことは十分に可能です。
「噛む」という当たり前の行為に、私たちの健康と未来が詰まっています。
今日の食事から、「しっかり噛む」を意識して、一生自分の歯で食べる生活をめざしましょう。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| 午後 | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
※祝日がある週の木曜は診療しております。
休診日:木曜・日曜・祝日